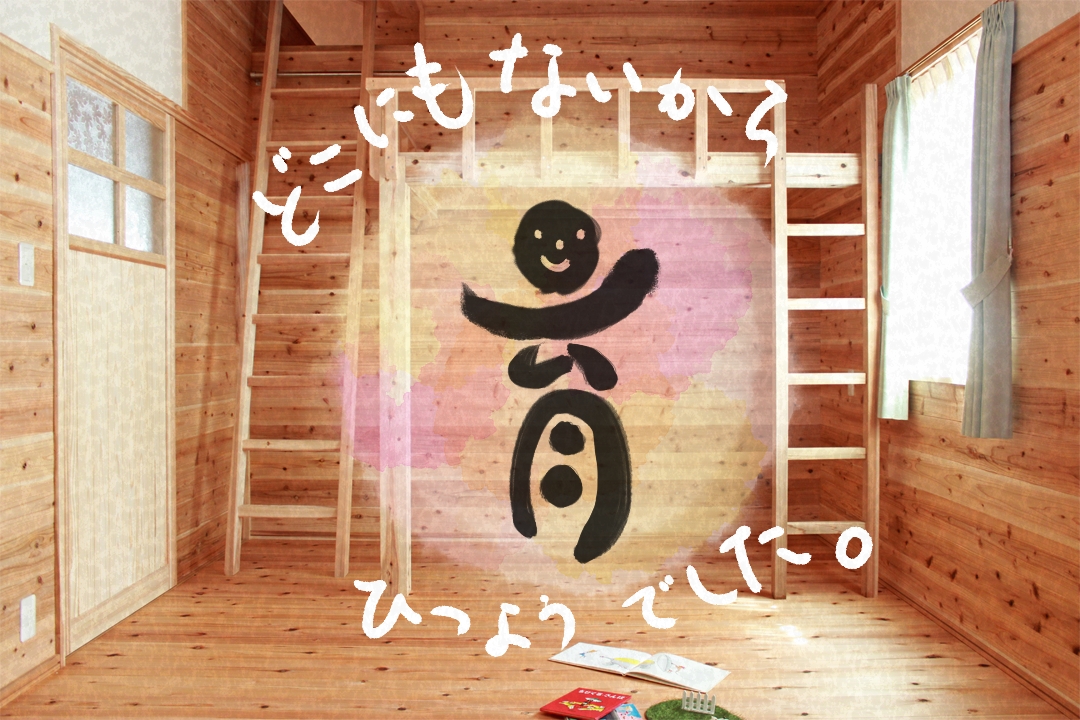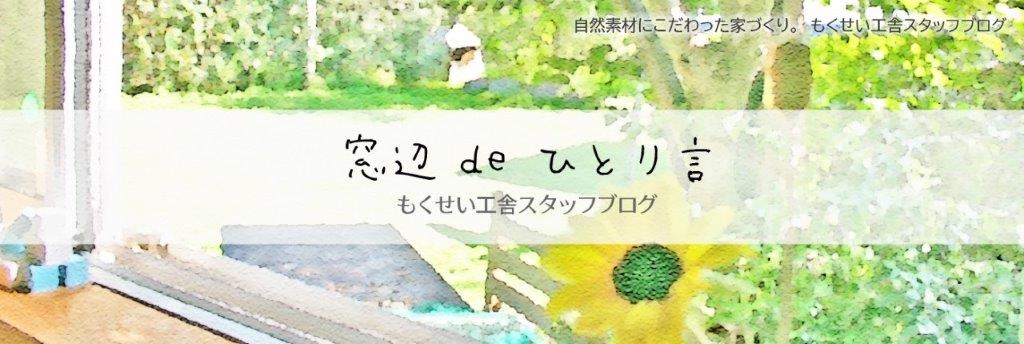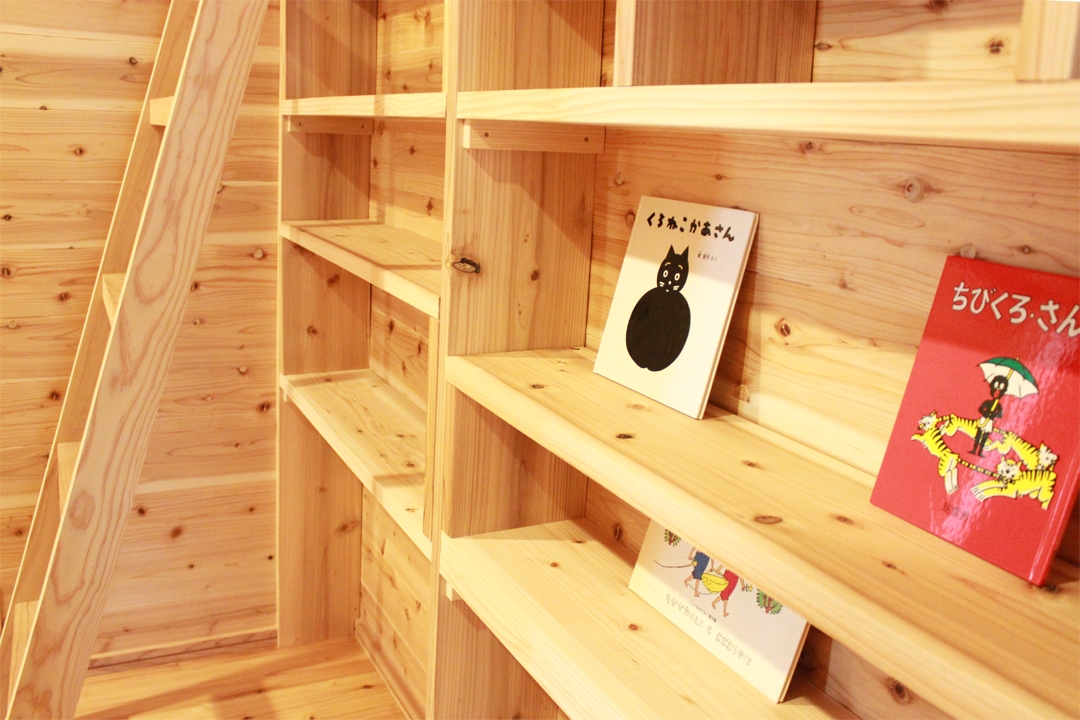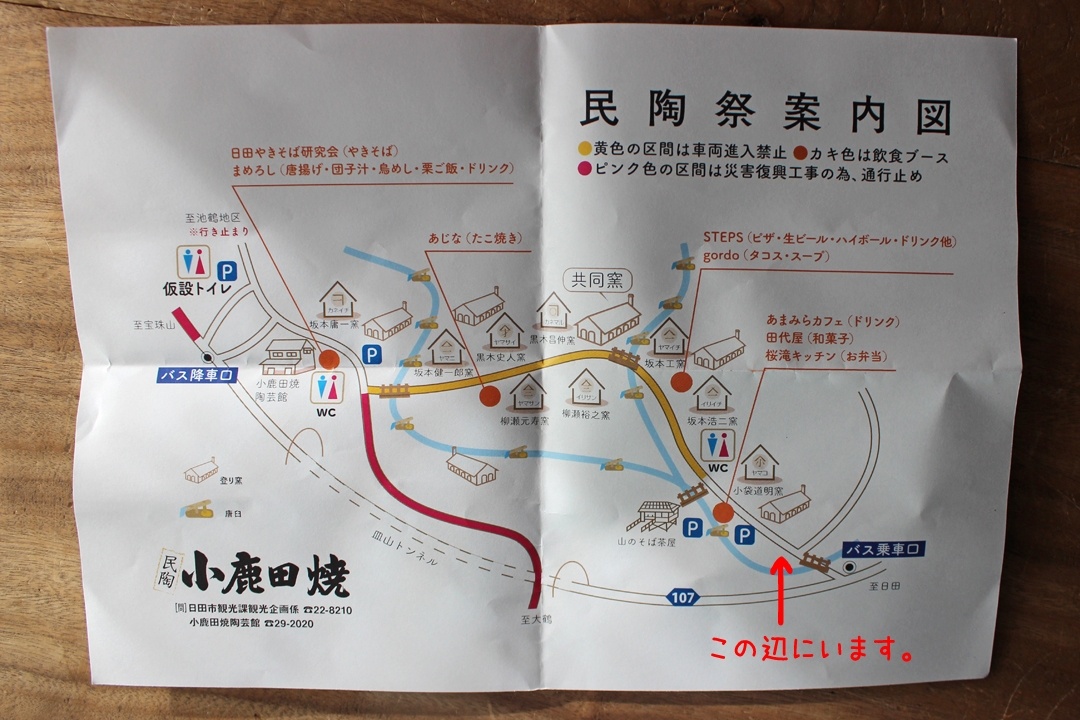「まずない」から、意味がある
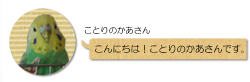
「自分にできることは、これなので、こういったものをつくりました。
誰か要る人いませんか?」と売るより、
「お困りですか?それ、お手伝いできると思いますので、一緒につくりましょう」という方が、売れやすいという。
スキルから、買ってくれそうな人(ニーズ)を探すんじゃなくて、
これがないと困る!(ニーズ)から、スキルを提供する感じだろうか。
今、もくせい工舎では、
「自然素材の家を建てる」スキルがあって、それを必要としている人を探す形になっている。
逆を考えれば、もくせい工舎のような家でないと困る人を探して、
その人が望むものを、どうやったらできるかを考えることが、後者に近いのかもしれない。
例えば、化学物質過敏症だったりする人だろうか。
ただ、医師免許や、そういった研究機関や、公的な立場でないので、
あたかも症状が改善したり、治癒したりといった効能や効果は、書けない。
言えるとすれば、低刺激であるということかもしれない。
それは、永家さんがもくせい工舎を立ち上げたきっかけに由来する。
相方である奥さんや、娘さんが化学物質に過敏で、
新築の店舗などに行くと、目がチカチカ、鼻はズルズル、
とても居ていられない。
かたや、自然素材で建てた我が家では、まったくそういった症状はない。
永家さん自身は、もともと新建材でもリフォームをしていた人である。
しかし、新建材メーカーの説明会などに出席する度、
そこに違和感を感じるようになる。
住宅ローンを組んで、これから何十年もかかって返していくのに、
その途中で、何百万と掛かる《補修》が当たり前の建て方に。
そして、自然素材でつくった我が家との、あまりの違いに。
永家さんが、そういった違和感を感じて、もう20年は経っている。
その間、新建材メーカーだって、病気にしたくて作っているわけではないから、
ホルムアルデヒドの発散量を抑えるなど、それなりの対策をとった製品も出てくる。
しかし、微量だから問題ないのかは、当事者でないと分からない。
少なくとも、そのことで困ったことがあるかないか。
その経験の有無、それに対応するスキルの有無が作り手にあるか。
それは当事者にとって、安心材料として、きっと全く違うことになる。
痛みの分からない人に、辛さは分からないからだ。
今、こういった先行きが分からない世の中で、
結婚や、子どもを産み育てるか否かまで、
これまでの《常識》や《一般的な流れ》が、全く形を変えている。
明日どうなるかもわからないのに、
家を建てたところで、払いきれるかも分からない。
ましてや、そうやって建てた家が、
いずれわが子に、実家じまいという負債として残るなら、
賃貸で身軽に暮らす方が、ずっと賢いのではないか。
体質に何もなければ、賃貸でもなんでもいいだろう。
かたや、新築の刺激臭や、古くなった建物のカビで困ることが多ければ、
そうはいかない。
そして、その賃貸に、そういった困りに配慮して、
隅から隅まで、極力自然素材だけで建てたような物件がほぼない。
あったところで、値段や場所、条件があうかどうかも分からない。
ないから、建てなくてはいけない。
困っているから、必要性・ニーズが出てくるのだろう。
先の考えで行けば、多分、そんな人のためにこそ、
家とは【建てる意味】があるのだと思う。
そして、極端な症状が現れないから無害かどうかも分からない。
刺激に過敏な人、小さな子ども、お年寄り。
そして、物言わぬペットまで。
一番配慮がいる人にあわせた環境は、
実は誰にでも優しい環境でもあるはず。
安さや、見た目や、機能以前に、
もっと大事なことがある。
それを考えつくした賃貸がないから、
家を建てる、その意味、ニーズ、必要性があるんじゃないかと思う。
それは、持家が損とか得とかいう以上に、
健やかに生きる場所として、必要だったということ。
そのためになら、
お手伝いできる何かがあるんじゃないか。
宇佐の山ん中の、小さい工務店に。

お困りの方も、そうでない方も、
よかったら、土壁の家を見に来てください。
見栄でも外聞でもなく、生きていく場所として
家を考えてみるヒントになれるかもしれません。