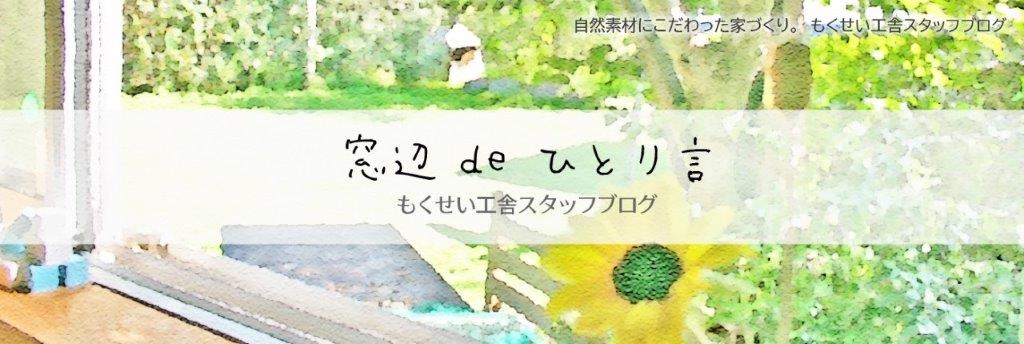お風呂の栓は、しましたか?
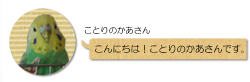
先日、ネットである記事を読んで驚愕しました。
それは、お風呂の自動お湯はりに関するもの。
お湯はりの自動のボタンを押して、「最初に少し水が出た後、一時停止するのは故障か?」との問い合わせに、
メーカーが答えた内容が元でした。
(わが家のお風呂は、10年以上使っているものなので、最新型はどうか分かりませんが)
確かに、早い段階で、一回止まる。
お風呂の栓をして、【ふろ自動】のボタンを押すと、
「お湯はりをします。お風呂の栓は、しましたか?」と音声が流れ、
ごぼごぼごぼごぼ...っとお湯が出だす。
数秒すると、一度止まるのですが、また続けてお湯が出だして、
指定位置までくると
「お風呂が沸きました」と知らせてくれるタイプです。
その記事は、わが家とは別メーカーのもの。
(メーカーによるのかも?ですが)
その最初にでるお湯は、配管に残っていた水なので、そのまま溜めない方がよいというものでした。
・・・・え~⁉・・・溜めてたよ?そのまま。
10何年も!
だって、最初に言うんだもの。
「お風呂の栓は、しましたか?」って。
「まずは、最初の水は流してください。それから、栓をしましょう」なんて言わないよ??
上記の記事の該当メーカーの説明書には、よく見ると書いてあるそうなのですが、
わが家の給湯はダイキン製。
・・・う~ん。そんなこと書いてないみたいなんだけど。
ネットでダイキンのQ&Aを見ても、「お湯はりが途中で止まった」の問いに、
「お湯はり完了までに、お湯はりと停止を繰り返す」との答えで、
最初の水は捨てるべし!とは出てこない。
ダイキンのAIチャットで質問してみるも、日常のお手入れとしての配管洗浄のページは出てきても、
やっぱり、最初の水は捨てよ!とは出てこない・・・。
う~ん。
メーカーによるのかもしれないが、
あまり気持ちの良い話ではないような。
だから、わが家では、
「お湯はりをします。お風呂の栓はしましたか?」と聞かれるのを、
あえて無視して、数秒栓を抜いたままにし、
水が一時止まったところで、シャワーで洗い流す。
その後、栓をして、給湯。
・・・としています。
最初に一時止まって見えるのは、お湯がないから「故障かな?」と気づきやすいだけで、
きっとお湯が溜まるまでは、
お湯の中で、出たり止まったり繰り返しているものなんだろうなと思います。
分かりにくいから、気づかないだけで。
とはいえ、私と猫以外、男ばかりのわが家。辞めた【便利機能】は他にもあります。
既に張ってあるお湯を循環させて温めなおすという【追い炊き機能】。
これもなんだか、あんまり清潔じゃない感じがして、使わないことにしました。
・・・すると、パイプユ●ッシュしても、変なビロビロが出てこなくなった。
(・・・いったい、毎日何に浸かってるんだか分かりゃしない。)
それで考えると、お湯と水を混ぜるタイプだった以前のお風呂は、
便利が過ぎない分、良い点もあったのかもしれません。
熱すぎたり、冷たすぎたり、入れすぎたりはあっても、
パイプの中まで気にしなくて良かったので。
台所の換気扇も、単純な作りの方が掃除がしやすかったりして、
便利が故の構造の難しさに泣くときがある。
システムキッチンのレンジフィルター奥の、
絶対手が届かない配管ダクトの中身を想像すると、
きっと汚れてるんだろうけど、どうしようもない。
掃除のしようもなくて、途方に暮れるのです。
う~ん。便利になるほど、構造や仕組みは、複雑になる。
複雑になるほど、素人じゃ、手におえない部分がでてくる。
ちょっとしたジレンマかもしれません。
(洗濯槽のカビの心配か、いっそ、たらいで洗濯か、みたいに。
洗濯だけに、難しい選択です。)
「お湯はりをします。お風呂の栓はしましたか?」
そう、声掛けしてもらう過剰な親切を他所に、
今日も又、完全無視の自己流で風呂を入れる日々なのでありました。
何でも自動化すると、退化しちゃうような気もしたり。しなかったり。

(※わが家のお風呂ではなく、同年代くらいのものを参考に載せています。)