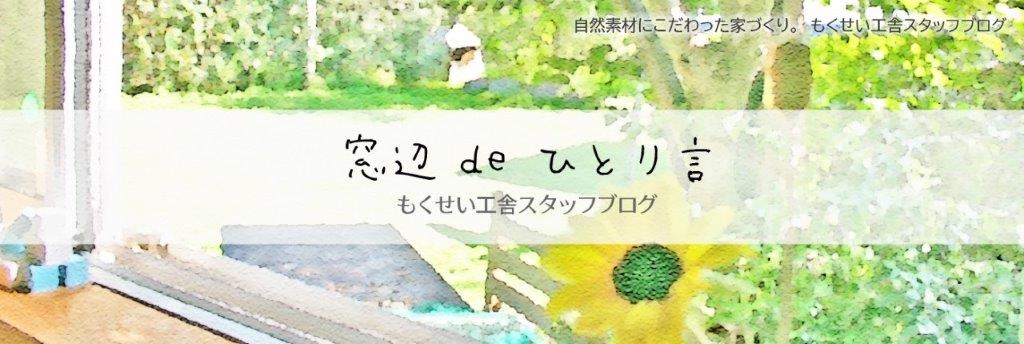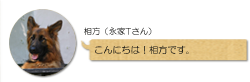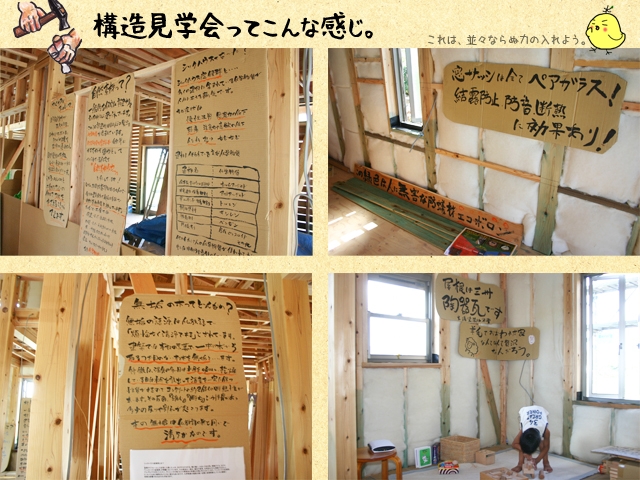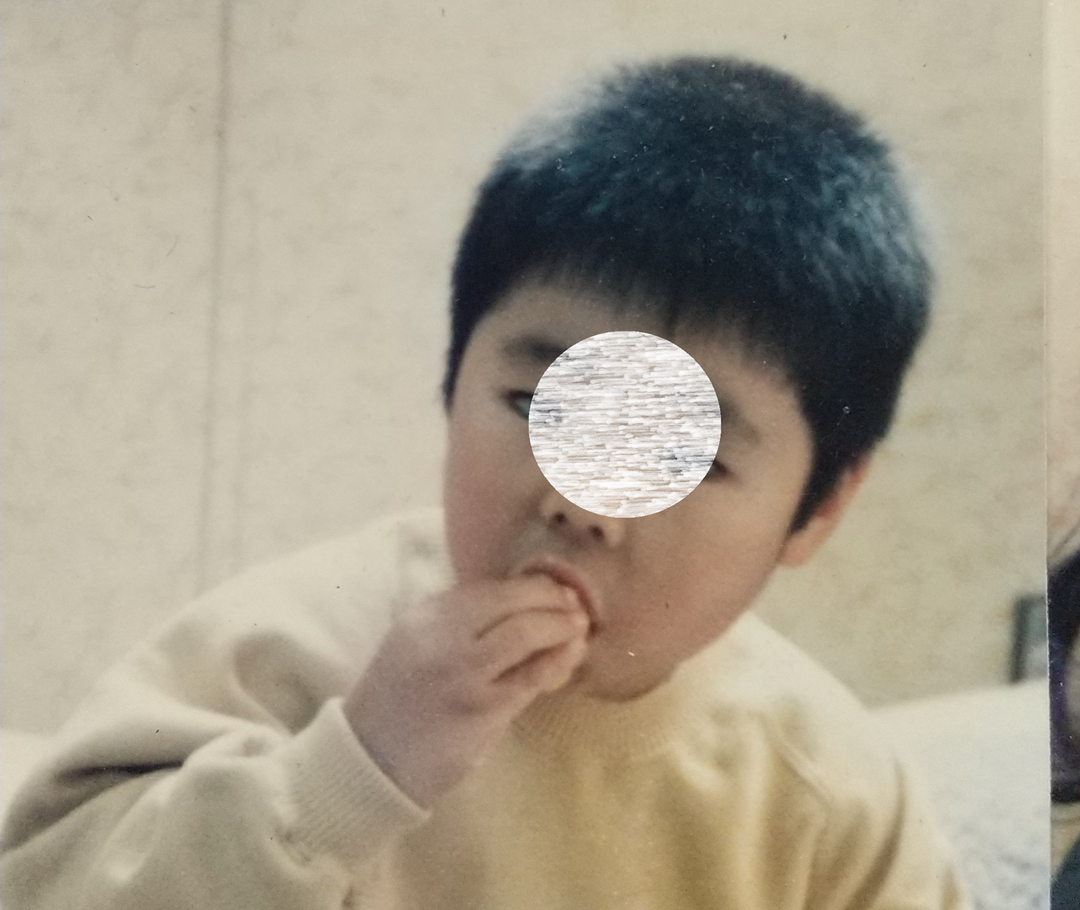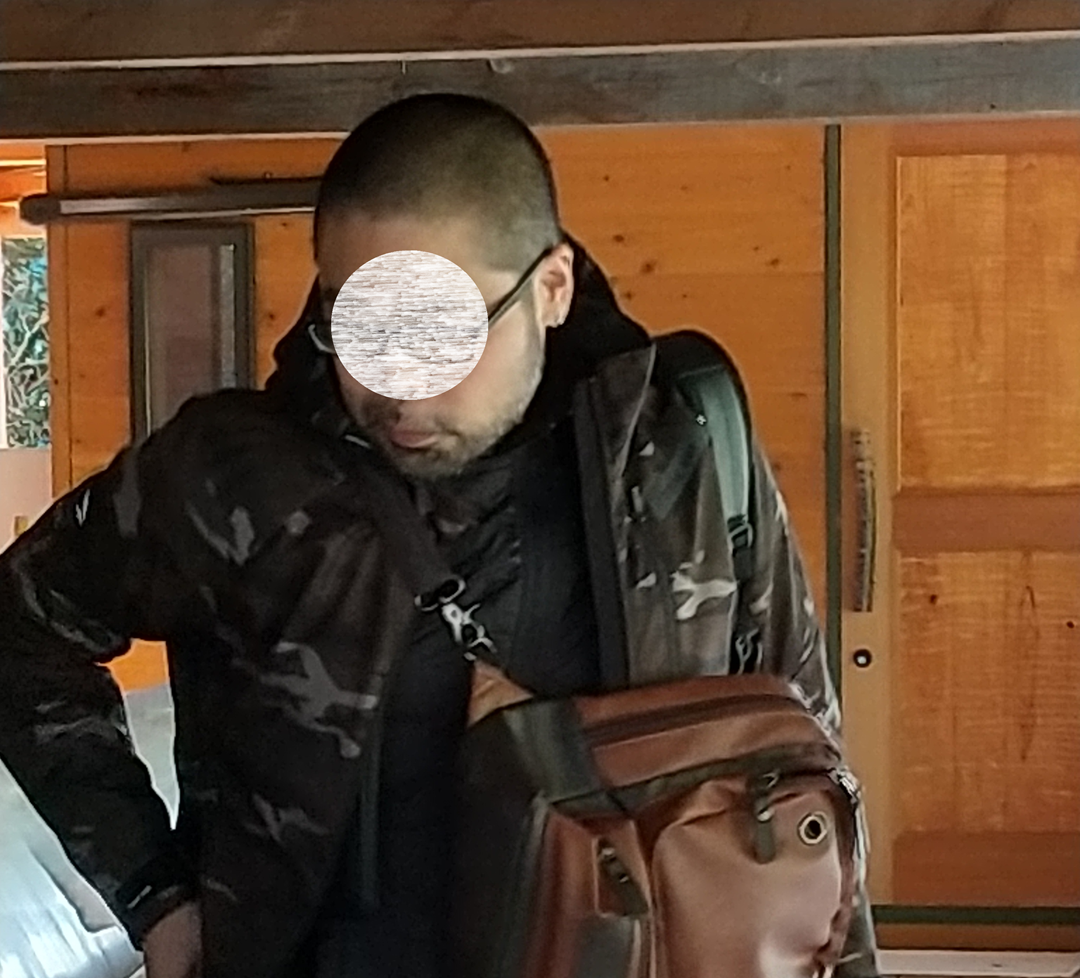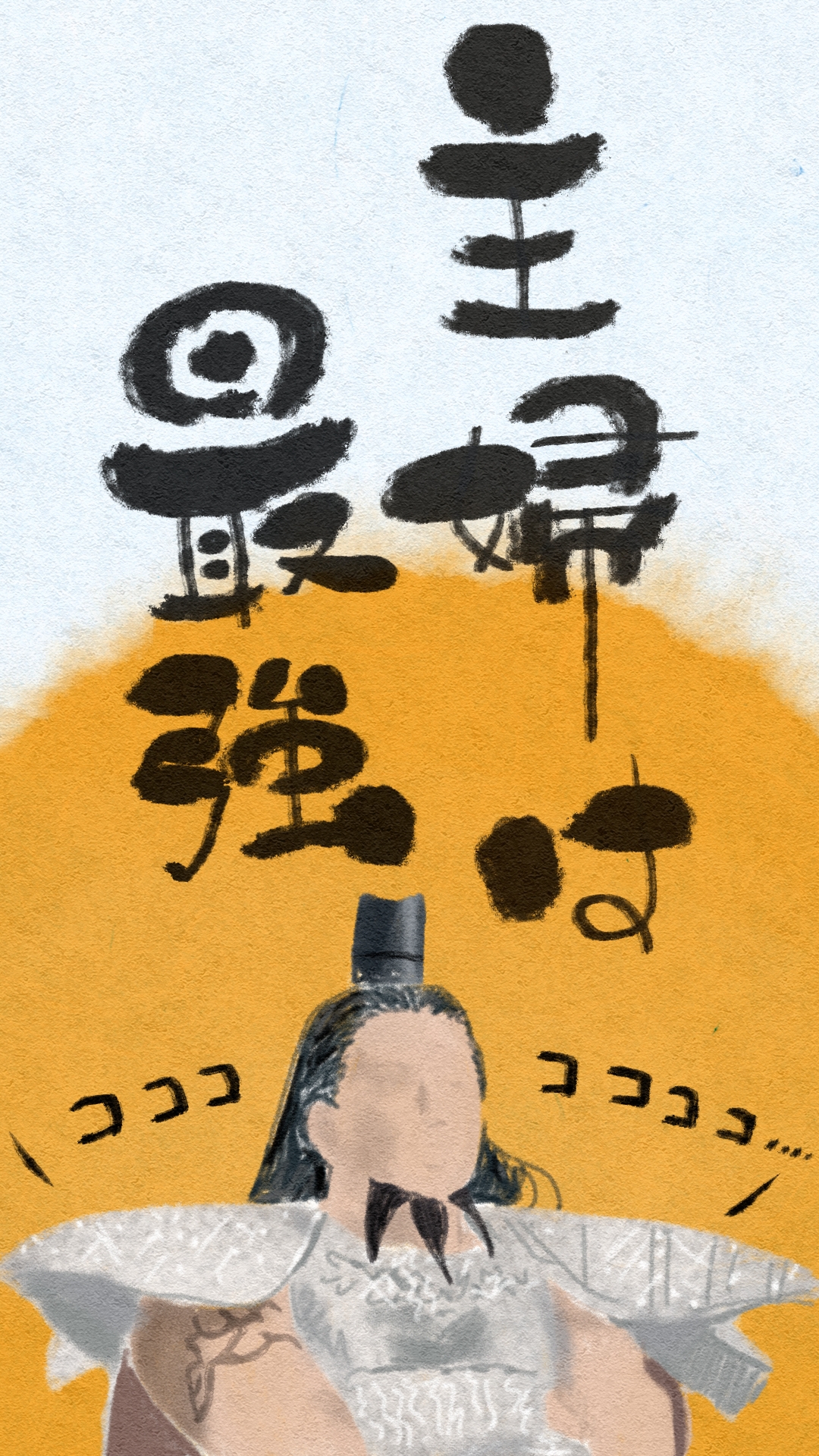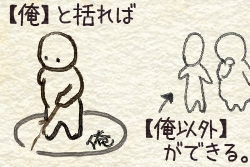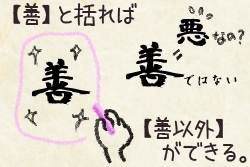で、で、出た~‼‼
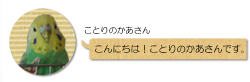
・・・出たんですよ、我が家に。
シロアリが。
実は去年も、羽アリを見て、
永家Tさんに、「紛れ込むこともあるから、2、3日様子を見て」と言われ、
出なくなったので、そのまま忘れていたシロアリ。
今年は天井に、二桁はいる!ヒェ~!
これは・・・ちょっと不味いぞ。
「紛れ込んだので」にしては、許容の範囲を超えている。
コロコロテープや、ガムテをモップに取り付け、
できるだけ駆除したものの、どうしたものか。
永家さんに聞くか?業者に頼むか?
いや、猫もおるし、どうしよう。
モヤモヤと寝付けぬまま(いつも寝てる場所にも出たので)、夜が明け、翌日。
私が相談したのは、人ではなく、
CopilotというMicrosoftのチャットAIでした。
私は、難しい話になると、頭がついていきません。
だから、AIに訊くときは、だいたい「小学生にもわかるように教えて」と伝えます。
すると、(悪く言えばタメ口、よく言えば)フレンドリーな応答が続く。
こちらも、物知りの友達に訊くように、緊張せず聞けるのは、なかなか良いです。
そのやりとりは、こちら!→【シロアリについて】チャットAIに訊いてみた
また、その中で教えてくれた、シロアリの生態については、別途【絵本風】にしてみました。
良ければ、『ぼくは、しろあり。』も、ご覧ください。

今回、総じて思ったのは、もくせい工舎のシロアリ対策は、かなりしっかりしているということです。
(チャットAIに、多少のヨイショは付き物ですが、手放しで「しっかりしてる!」と褒められたので。)
それでも、紛れ込むことがあるのも事実で、
その際どうしたらよいのか、事細かく訊くことができました。
チャットAIの良い所は、どんな変な質問をしても、
嫌な顔一つされないことです。
ともすれば、気を害さないよう、つたなく言葉を選ぶうちに、
肝心かなめのことが、ズバッと訊けなかった!なんてこともありません。
直球で、「そうはいっても、実際問題、入って来てるし、不安なんだけど!」を吐露できます。
たいへん気が楽!
しかも、偏らない!まんべんなく、色々な方面から教えてくれる!
(訊いてもいない、スピリチュアルな意味まで教えてくれました。なんでも、"変化"や"新しい始まり"の象徴らしいです。
それでも、なるべく家には来ないよう願いたい。)
対ヒトだと、その人の知る限りのことしか出てこない。
その辺は、AIサマサマというか、本当に助かりました。
ちなみに、出てきたのはその日だけ。
翌日には姿を見ませんでした。
ただ、用心はしておきたいと思います。
どんなに誠意を尽くしたつもりでも、住宅業界はクレーム産業と言われます。
それは、家というものが高額すぎるから。
そして、営業時にはメリットばかりを強調されるから。
(反対を言えば、恋愛と一緒で、最初はイイとこしか、目につかなかったのかもしれませんが。)
しかし、そこに故意がなかったにしても、
お施主さまは、その家、その現場に、
誰よりも長く居る人。
設計した人より、工事をした人より、
ずっと長く現場にいて、現場の【実際】を知る人です。
高額な金額を払って、聞いていた話と違っても、
それは、瑕疵担保の範囲ではありません。
クレーム産業と言われると、お施主様=クレーマーのように感じそうですが、
実際は、「責任取れ!」と、無茶な言いがかりを付けているわけではなく、
ただ、高額な、「しっかり選んだつもりの家」で、
思いがけず起こったトラブルに
困って、不安でいるのだと思います。
まずは、その不安な気持ちを思いやり、
しっかりと納得いく、分かりやすい説明をして、
しっかり応対できる工務店かどうか。
そこが、「次に頼むときも」の感覚を産み、
他の人にも勧めたい、リアルな、草の根的な口コミにつながるのではと思います。
広告の世の中、SNSの世の中にあって、
草の根的口コミがどんなに心強いか。
全国チェーンのハウスメーカーではなく、
地域に根差して生きる工務店ほど、
それはどんなに、自らを鼓舞する【光】となるか。
知らない誰かの「イイね!」より、
知っている誰かが、嬉しそうに話す「いいんよ~」の方が、
心に響くし、実際に自分も行ってみたくなる。
それは、顔が見えない誰かの【バーチャル】ではなく、
正真正銘の、顔が見える【リアル】だからです。
ちなみに、チャットAIも手放しでほめる、もくせい工舎のシロアリ対策。
明日まで、構造見学会で、実際にご覧になれます!
こちらも、ぜひぜひお越しください。