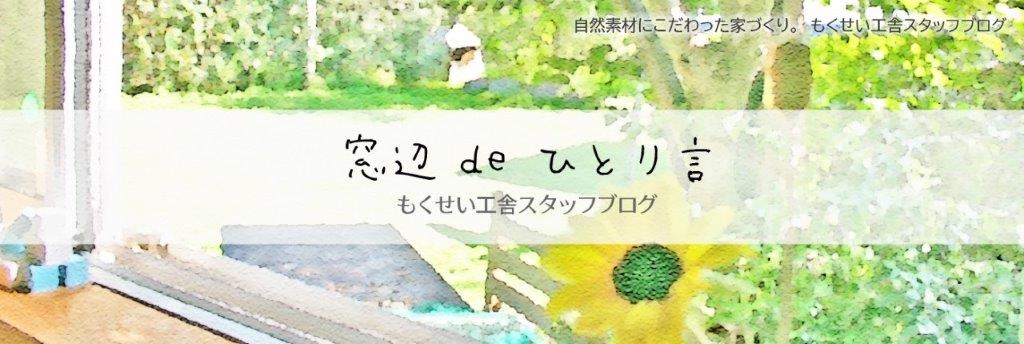責任転嫁は、なぜ【嫁】なのか。
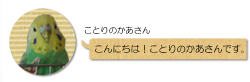
絶賛、お盆中ですね。
たった今、この瞬間も【嫁】業務に、まい進されている、全国の【嫁】業のみなさん、お疲れ様です!
さて、先日の新聞に脳活の問題が載っていました。
添()/転嫁
で、同じ読みで、違う意味になるよう()内に漢字を入れるもの。
お盆時だから、ドキっとしたのか、ギクッとしたのか。
そういえば、責任転嫁の転嫁って、なんで【嫁】って書くんでしょうねぇ。
私は、万人受けする、誰にでも可愛がられるタイプの人間ではないので、
嫁としても、浮いています。浮きまくっています。
(己の不徳の致すところ、身から出た錆。
こればかりは、相性もありますから、仕方がない。)
その昔、防虫剤の《タンスにゴン》のCMで、
「亭主 元気で 留守がいい」なんてフレーズが流行りました。
(いいわけになるけど)それって、嫁にも当てはまるのではないか?
気に入られているのに、行かないのは不義理ですが、
気に入られてないのに、行くのは、もはや嫌がらせでは?
(犬が苦手な人の家に、わざわざ犬を連れていくようなもんでは?)
そう思うこととし、なるべく、近寄らない。
請われれば、喜び参じるけれども、
微妙な気持ちにさせるくらいなら、
嫁だって、元気で留守がよかろうと、そういうスタンスでおります。
そんな、とても褒められない嫁だから、先ほどの責任転嫁の【嫁】の字に、ドキッとしたのではありますが、
そもそも【嫁】の字源は、なんだろう?
それは、そのまま、【家】についた【女】のよう。
息子に良(よ)い女(め)が来た。
それが、嫁ということみたいです。
責任転嫁の【転嫁】は、「嫁に転ずる」。「嫁が他家に移る」つまり、再婚することらしく、
本来あるべきところから、他所に移すの意。
本来、責任のあるべきところから、他所へ移す。
【責任転嫁】となったよう。
古語の被(かず)ける、の与える、身に付けさせる、から
同義として【嫁】というのもあるらしいのですが、こちらは私じゃ、よく分からず・・・。
それにしても、【男】が含まれる漢字は圧倒的に少ないものの、
【女】が含まれる漢字は、山ほどある。
【女】が【良】い状態だと【娘】で、
【女】に【波】がつくと【婆】で、って・・・。
なんかあんまりじゃなかろうか。
じゃ、
【男】に【良】で、【イケメン】か?
【男】に【波】で、【じいじ】か?
それを言い出したら、
【飯】のことばかり聞く【男】は、もはや【夫】と読んでもでもいいのでは?
もはや、大喜利状態で考えたくなる。
そもそも、【嫁】の対義語は、【夫】ではなく、【婿】だというから、
こっちも女が入ってる。
これも、男性側が、あくまでも女性側の「家に移る」の【婿】。
なんとなく、主が男で、女がサブ的な感覚が否めない。
それは、漢字ができた、古代中国で、女性が男性に隷属させられていたからと言われていますが、
・・・なんだかなぁ。
そう思う、出来損ないの【嫁】なのでした。
というか、こんなことを面白がって、どんどん考えずにおれない女が、
【嫁】にきたら、扱いにくくて当たり前だよな、と納得する次第です。そりゃ、やだよなぁ。メンドクサイもん。

ウ冠は、屋根を表らしく、(諸説あるようですが)屋根の下に、女がやすらぐさま。
女の人ばかり右往左往して、ちっともくつろげない場所は、安らかとは程遠い気もします。