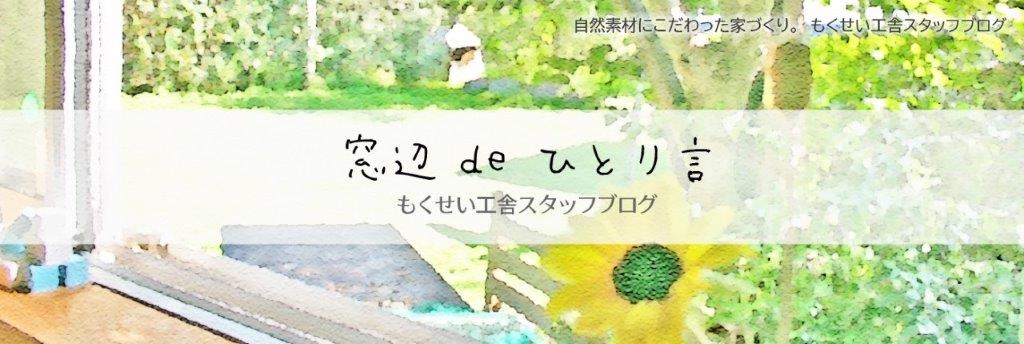国の宝となる人は
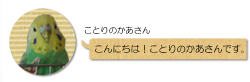
映画『国宝』を見てきました。
「何度も足を運んでいる」とレビューにあって、気になって仕方がない。
『ボヘミアン・ラプソディー』や『侍タイムスリッパー』など、
もう一回どころか、何回も見たくなる、
あの中毒性が、『国宝』にもあるのでは?と、
その、惹きつけられる理由が知りたかったからでした。
観た感想としては、
すごいんだけど、綺麗なんだけど、
なんだろうこの言葉にできない感じ。
観た直後でも、「あ~、面白かった!」「もう一回見たい!」という点では、
『侍タイムスリッパー』の方が、スッキリ痛快感がある。
じゃ、面白くなかったのかといえば、そうではなく、
すごい究極のものを見せつけられて、
圧倒されつつ、モヤモヤしている感じ。
これは、アレだ。『おみおくりの作法』を見た時と似ている。
究極のものを見せられて、「おまえはどうなんだ?」と問われている気がするのです。
任侠の家に生まれ、親を殺され、天涯孤独になった喜久雄。
歌舞伎の家に部屋子として引き取られます。
御曹司の俊介とともに、切磋琢磨しながら、
芸を極めていくのですが、
その極め方が、もうスゴイ。
「歌舞伎を上手にしてくれるんだったら、他は何もいらない」
悪魔と取引してでも、極めたい何かなんて私にあるだろうか?
芸のためなら、役を得るためなら、演じるためなら。
誰かを利用してでも、手に入れたい、極めたい【こと】。
私などは、どこか《人の目・人聞き》の方が気になる。
そこまで、貪欲になれるものなど、ないのです。
一つのことを、他を犠牲にしてでも極めたい姿というのは、
一種の狂気のよう。
正気の沙汰じゃない。
「お前には、そこまで賭して、打ち込める何かなんてあるのか」
それを問われ続けて、見終わったような気がするのです。
『おみおくりの作法』という映画も、主人公の民生係のジョン・メイが、
ひとりで亡くなった人たちのために、心をこめたお見送りをする話でした。
結果的に、彼自身も孤独なまま亡くなってしまうのですが、
「例え、現実的には報われないとしても、
誠意をこめた行いを、お前はそれでもできるのか?」と問われているようで、
やっぱり見終わった後、スッキリせず、モヤモヤする。
でも、その後、何年経っても、そのことを思い出しては、
また問い続ける。
そう、『国宝』も、『おみおくりの作法』同様、
私にとって、問い続ける映画だったのです。
主役の、吉沢亮さんの狂気をおびた演技もさることながら、
少年時代の喜久雄役の踊りに、目を奪われる。
華があるとは、こういうことなのかと思う。
目が追うのです。
横浜流星さんの、演技力のすごさにも驚く。
役によって、全く違う人格に見える。
全く蔦重じゃない。
何の役をやらせても、「元アイドルグループの○○の演技」にしか見えない人もいるが、
この人は全く違う。憑依的なのです。
でも、でも、一番の圧巻は、
人間国宝の女形・小野川万菊を演じる、田中泯さん!
目線一つ、短いセリフ一つ、佇まいから何から、
もう、別格の存在感!
万菊が演じる、鷺娘の息を吞むような美しさ!
お年を考えると、とても《娘》ではないんだけれど、
若くて、ビジュアル的な美しさでは、吉沢亮さんなんだけれど、
内から発するものが、雰囲気が、とてつもないのです。
あれは、また見たい!何回も見たい!
そうか、スッキリ痛快な
【誰にでも分かりやすいエンターテイメント】を見たわけではないけれど、
喜久雄の人生を通して、その狭間にあった、
究極のエンターテイメントをもう一回、二回と見たくなるのだと思います。
歌舞伎に全く詳しくない、おそらく歌舞伎座に一生行くこともない私が、
映画の一場面を通して触れた、国の宝に値する芸術だったのだと、
3時間座りっぱなしで、痛む腰を押さえつつ、思い返すのでした。
後半、喜久雄が呼ばれて、引退した万菊さんを訪れるシーンがあります。
人間国宝・万菊が臥せっていたのは、
古びた木造の小さなアパート。
部屋には、市松人形と小さな文机。
万菊さんが、喜久雄のように「歌舞伎の上達の他には、何もいらない」と取引したかは分かりませんが、
そこにあったのは、芸だけに生きて、引退後、何も持たず生を終えようとする姿でした。
もうこれ以上、【美しさ】を追求せずに済む「やっと赦された」安堵感。
唯一無二の、国の宝になるというのは、
生半可じゃないのだと思いました。
家に帰ると、ちょうどテレビで、桂米朝さんが落語をやっていました。
冒頭、「噺家なんて、喋るのを取ったら、何にも残らない」と言うのを聞いて、
この人たちも、噺という芸ひとすじの生なのだと思い、映画と重なりました。
本棚に、途中から難しくなってきて、アタマがついていけず、
積読になったままの『三流のすすめ』という安田登さんの本があります。
その中で、
一流とは、1つのことの専門家。
三流とは、色々なことをするひと。
それを軸に、三流であることの素晴らしさを教えてくれます。
喜久雄は、歌舞伎が全てでした。
彼から、歌舞伎を取ったら、何も残らないくらいに。
かたや、決して一流にも、国宝にもなれない【三流】の私には、
たくさんの、ささやかな《たいせつ》があります。
どっちが良いかなんて分かりませんが、
絶対真似できない、極みを見せられて、
爽快感とは一味違う、反芻感というか、
問いを与えられた映画でした。