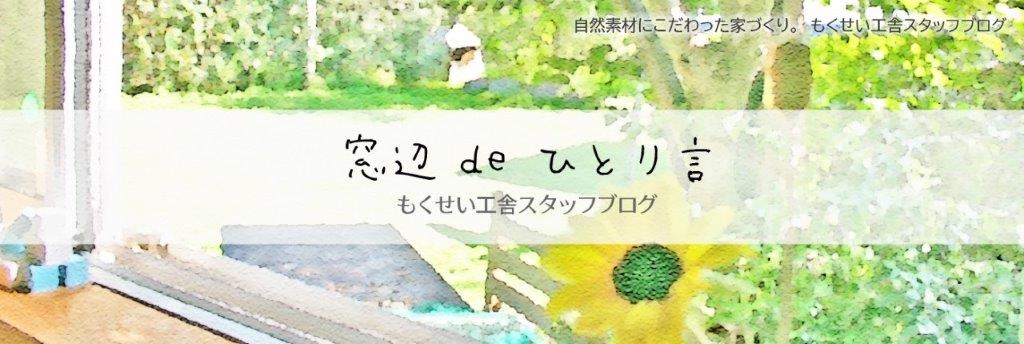#の外の世界
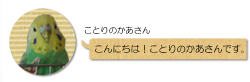
前回、過食症と拒食症だった話を書きました。
私は、SNSで個人の発信をしませんが、
#拒食症、#過食症とタグ付けされれば、
それに関連した情報だったり、同じことで悩む人に
気づかれやすくなるのだと思います。
体験談を語ることは、
また、誰かの体験談を聞くことは、
「分かる、分かる」の共感を得られる。
自分一人が苦しんでいるわけではない。
それは、どんなに癒されたり、勇気づけられるか。
同じ悩みを持つ者同士、直接的ではないにしろ、
どこか繋がりすら感じます。
その一方で、私を救ってくれたのは、
子猫のまっすぐな食欲でした。
子猫は#拒食症とも、#過食症とも検索しません。
「生きる意味」や「生きる価値」に悩んで、
自分を傷つけたりしません。
ありのまま、自然なのです。
つまり、#の全く外側にいた存在が、
私の目を覚ました、ということです。
もう、放送が終わってしまいましたが、
『舟を編む~私、辞書作ります』(主演:池田エライザさん)というドラマがありました。
その中で、経費削減のため、デジタル一本で辞書をつくれという社長に、
なんとか紙媒体のメリットを伝えるべく奮闘する姿が描かれます。
その時出てきたのが、「セレンビリティ効果」という言葉。
セレンビリティとは、思わぬものを偶然に発見する能力。引き寄せる力のこと。
同じことで悩む、ということは、似たような思考パターンだということです。
そして、誰かがそれを乗り越えた体験は、
ある意味、希望を見出せますが、
その体験そのものを、追体験することはできません。
私を救ってくれたのは、「同じようなことに悩む人」ではなく、ただの子猫でした。
つまり、モノの見方を180度変えようと思ったら、
全く違う考え方の人、#タグの外の世界にふれないといけない。
日頃、「思ってもみなかった」ことに出会うしかない。
思えば、私がもくせい工舎に出会ったのは、
フリーペーパーの広告を「偶然」見たからでした。
「セレンビリティ」そのものです。
木は好きでしたが、#自然素材とか、#漆喰の家なんて、考えてみたこともなかったのです。
SNSの時代にあって、#の外側、
こんな家があるとも知らない方に、どうやって伝えるのか。
とりあえず、関係あることないこと、色んな方面から記事にする。
それで、偶然見つけてくれたりしたら、本当に奇跡的。
私は、古臭い、時代遅れのアナログですが、
どこかの誰か、#の外の人に、届けばいいなぁ。
また、「家と、全然関係ないやん!」的な笑えるネタ、どうでもいい話なども折込つつ、
多角的な面から、家や暮らし、自然なこと、
そして家のことを考えてみたいなと思います。

#の世界は「情報」まみれ。
それに疲れたら、やっぱり#とは正反対の、自然にふれなければいけない。
人と比べて落ち込むくらいだったら、スマホは置いて、散歩に行く方がずっと良いのです。
人を癒せるのは、自然だけ。
あの子猫も、まさに、自然そのものだったのです。